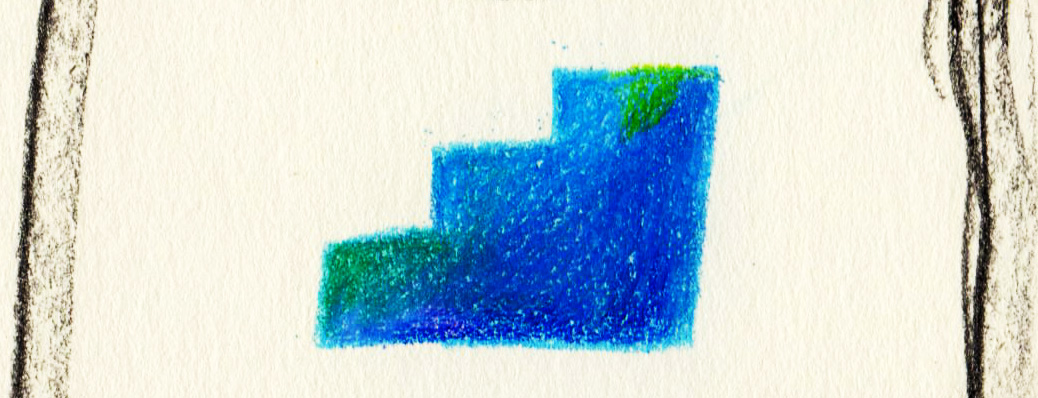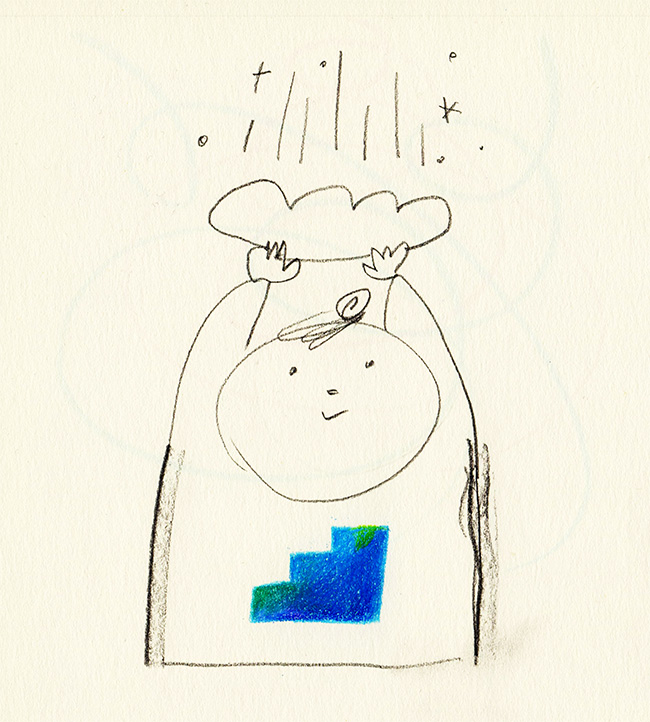バスに乗っていたら、おばあさん二人の会話が聞こえてくる。
「ほら、もうすぐよ。このあたり」
「あなた、ほら、言ってたじゃない、階段のある家でしょ」
「そうよ、青い階段のある家よ」
「青ね、青」
首を伸ばして窓の向こうを注意深く観察する二人と一緒に、わたしも外を眺める。
朝の光がまぶしく、瞼はすぐさま閉じようとする。
眼球を包み込み守るため。
バスはのろのろ、それでも歩くよりは速く進んでゆく。
「ほら、あそこよ」
とおばあさんの一人が言う。
白い壁にサファイアブルーの外階段が映える建物を、わたしも「あ」と見つけていた。
あれがもし、 “青い階段のある家” じゃないんだとしたら、もうほかには見つからないんじゃないかというくらい、目の覚めるような青。
手すりも柵も、歩く段々も、青。
「あれね、青い階段だわ」
ともう一人のおばあさんも納得する。ほっとして黙る。
「ね、青い階段でしょう」
バスが停まって、二人は降りてゆく。
青い階段の家では、誰が待っているのだろう。
わたしは何度も眺めているのに、このバスの窓の外に青い階段のある家があることを知らなかったことにまざまざ驚きながら、そのまま座っていた。すぐに閉じようとする二つの瞼といっしょに。