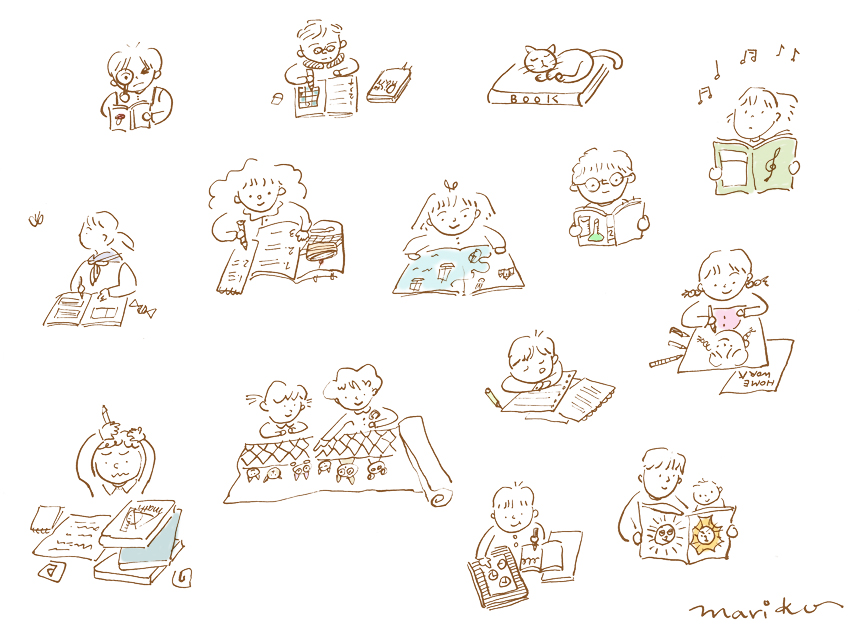わたしはさくらももこさんにお会いしたことがないけれど、風や光のように、さくらさんがこの世界のどこかにいる世界をたしかなものとして信じ、その同じ世界の別のところで、じぶんも生きていた。
誰かが恥ずかしそうにモジモジしていると、「ハレハレ君みたいだね」と言うし(相手がハレハレ君をちっとも知らなくても)、お寿司を食べる時は、友蔵がまる子と一緒に花輪君行きつけの高級寿司店へ行って、金額を気にしっぱなしでシメサバばかりを注文していたことを思い出す。思い出す、という表現はすこし奇妙で、それは漫画のなかの話であり、わたしの思い出ではないし、友蔵もまる子も知り合いじゃない。でも、思い出すのだ、あの時のことを。初めてあの話を読んだとき、わたしは “シメサバ” がどんなお寿司か知らなかったし、学校があんまり好きじゃない小学生だった。今は、お店で鯖寿司を見かけるとパブロフの犬となる。
中学生のとき、「読書の時間」というのがあった。本当は、今まさに読んでいるところの本を持参して、授業中に黙々と続きを読む・・・ということを要求されていたんだと思うが、大抵わたしは直前に図書室へ行って本を借りていそいそ教室へ戻り、チャイムが鳴るころ、その本の一ページ目をめくるのだった。それでいざ読みはじめてみたら、「はっ、これで45分読み続けるのはしんどいかもしれない」ということも当然あり、その場合は睡魔との戦いとなるわけです。
ある日の読書の時間に、さくらももこさんのエッセイを愉快に読んでいた。たしか『ももこのいきもの図鑑』(マガジンハウス)を読んでいたとき、先生がわたしの机の隣に立って、「それは “本” じゃない」と言った。わたしは一冊目を早く読み終わった場合に備えて借りた、さくらももこ著『あのころ』(集英社)も机に載せていたように思う。卵のかけらやボタンで表紙の絵が描かれたかわいい本。というわけであいにくながら、先生の(おそらく)求めている、”挿し絵のない、文字ばっかりの、むつかしい本” は、わたしの手元にはないのだった。今も時々、先生の言っていた “本” はどんな本のことかしら、と考える。志をもって読みはじめ、ページに線を引いたり、分からない言葉を調べたりしながら、壁をよじ登るように一歩ずつ読むような本のこと?
静かな授業中だったので、わたしは何度も笑いをこらえた。おそらく読書の時間は一年くらいはあったのだろうか、わたしが読んだ記憶があるのはさくらももこさんの本と、授業のはじまる4月の最初の日に持参した司馬遼太郎の『竜馬がゆく』(文藝春秋)だけである。
漫画や文章やイラストで、さくらももこさんの生み出した世界はおかしい。おかしいというのは、面白いのおかしいと、奇妙であるというおかしい、かわいいというおかしい、いろんなおかしいの凝縮である。(まる子はお菓子が好きである。)
子どもと大人、神様とカエル、お金持ちとそうでない人、太陽とやかん、昔と今、あっちとこっち。小さいものも大きなものも、しゃべって泣いて笑っているおかしな世界。
本を通して、そういう世界に遊びに行かせてくれて、あっちとこっちを繋げてくれて、ありがとうございました。これからもどしどし、ページをめくって遊びに行きます。